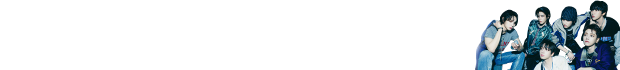「ゆれながら咲く花」この世の中を作った大人たちに問う
鋭い破裂音とともに空から椅子が落ちてきた。入学説明会に参加するため学校を訪れた保護者と教師たちの目の前で、“生徒たちが最も幸せでいられるように”作った学校という校長(パク・へミ)の言葉が、割れたガラスとともに空中に散らばった。その瞬間、この無機質な建物の中で、それぞれ別の方向に噴出していたり、抑えられていたり、もしくは隠れていた人々の欲望が、その姿を現した。KBS「学校」のシリーズであるが、「学校5」ではなく「ゆれながら咲く花」という名前を選んだことから、このドラマの方向性がはっきり見える。「ゆれながら咲く花」は問う。「今、この学校とはどんな場所なのか?」と。そして、質問を正確に見てみよう。「学校とはどんな場所でなければならないのか?」ではない。「ゆれながら咲く花」は当為や定義に関する問題ではなく、今の学校がどんな場所なのかを聞いているのである。
 “スンリ高校(勝利高校:VICTORY HIGHSCHOOL)”という露骨な名前が書かれてある学校の校門を通るその瞬間から、事件が絶えない学校での一日が始まる。“パンシャトル”(代わりにパンを買ってくる使いを意味するネット上の新造語)から喧嘩まで日常化されている暴力、先生を気にすることなく生徒たちがうつぶせになって寝ている授業、学校でのことなら何でも関わろうとする保護者はもちろん、先生を師匠として接しない生徒たちの顔色を伺わなければならない教権など、「ゆれながら咲く花」が描く問題は、今の学校が生徒、教師、そして、保護者といった当事者それぞれにとってどんな意味なのかを問う。
“スンリ高校(勝利高校:VICTORY HIGHSCHOOL)”という露骨な名前が書かれてある学校の校門を通るその瞬間から、事件が絶えない学校での一日が始まる。“パンシャトル”(代わりにパンを買ってくる使いを意味するネット上の新造語)から喧嘩まで日常化されている暴力、先生を気にすることなく生徒たちがうつぶせになって寝ている授業、学校でのことなら何でも関わろうとする保護者はもちろん、先生を師匠として接しない生徒たちの顔色を伺わなければならない教権など、「ゆれながら咲く花」が描く問題は、今の学校が生徒、教師、そして、保護者といった当事者それぞれにとってどんな意味なのかを問う。
まず、四角い教室の中にいる様々な生徒たちを見てみよう。勉強ができる生徒とその子を嫉妬する生徒、当たり前のように遅刻し平然と授業をサボる生徒、学校には毎日欠かさず来るが勉強する代わりに昨夜取れなかった睡眠を取る生徒、授業時間にはまるで死んでいるように見えるが休み時間には生き生きとする生徒などがいる。何より、勉強は嫌いだが大学には行きたいと思う大多数の生徒がいるのだ。隣の席に並んで座ることなく、一人ずつ座っているこの子たちは、同じクラスの友だちに淡い恋心を抱く前に、目に見えたり見えなかったりする序列の中で自分たちの位置を確認し、嫉妬と劣等感を先に学ぶ。この子たちにとって学校とは、大学という生徒たちにとって共通の恐怖に支配されたまま、それぞれの方法で耐えなければならない収容所だ。
教師たちも彼らとあまり変わらない。「まだ……子どもたちの手を離す時ではない……」と自分自身に言い聞かせながら、生徒たちの手を自分の手で叩くチョン・インジェ(チャン・ナラ)は、些細な出来事一つで地位が揺れてしまう臨時教師だ。現実を静観したり冷笑したり、現実に安住したり対抗したいと思う教師たちにとって、学校は無力感と戦わなければならない組織だ。そして、保護者たちにとって学校は、自分の子どもが大学に進学するにおいて少なくとも邪魔にはなっていけない組織であり、子どもを通して投影された自分のアイデンティティーを確認する場所だ。このように、誰かにとっては監獄であり、誰かにとっては仕事である学校は、どの組織や空間よりも様々な面を持った人々が一緒に集まっており、一つに融合できない欲望が衝突する場所だ。
そして“ソウル市内の高校178校のうち、149位である”江北(カンブク)の高校という明確な地域性と序列を明かしたうえでスタートした「ゆれながら咲く花」のもっとも大きな美徳は、この欲望の激しい衝突を深く覗き込んで、思慮深く描き出すという点だ。授業中、一つのチームになったわずか5~6人の子どもたちの間でも、お互いに望むことがはっきりと違う。まして、一つのクラスに集まったおよそ30人の子どもたちも、授業の方向を一つに決めることができない。成績が悪くて迷う子どもたちと成長の過程で迷っている子どもたちのうち、どちらのほうが大切ではないと断言できるのか。家庭でちゃんと育てられなかったオ・ジョンホ(クァク・ジョンウク)が教室の中で見せる未熟で荒い人情の闘争も、子どもたちが眠らない授業をしたいと思うチョン・インジェの理想も、将来を左右する自分の子どもの成績が学校の目的でならなければならないと信じるミンギの母(キム・ナウン)の望みも、その人々にとってはそれぞれ正当な欲望である。
「ゆれながら咲く花」は質問を投げかけるドラマだ。このドラマは、学校内の当事者たちが提示する問題のうち、どれが正しくてどれが間違っていると判断することはせず、愚かな楽観主義や性急な代案で包むのでもなく、まず各主体たちの欲望を覗き込んでいる。それはじっくりと見てこそ気づくことができ、長く見てこそ理解できるような質問を投げていることになる。知的障害を持つ生徒ハン・ヨンウ(キム・チャンファン)と問題児オ・ジョンホの衝突をヨンウを転学させるための理由にしようとする学校に向かって、「学校とオ・ジョンホ、何が違いますか?」と聞く。模範答案の通りに書いた論述の答案でも高い点数をあげることができないという教師に向かって、「それでは、模範答案はどうして存在するんですか?」と聞く。
 しかし、時には質問を投げるだけでは足りない。「ゆれながら咲く花」が珍しくちゃんとした質問を投げた理由は、成長痛と思い込んでしまうには、大人になっていく過程であまりにも苦しむこのかわいそうな子どもたちを、これ以上放っておくことができなかったためではないのか。だから、重要なのは「学校はどんな場所なのか」に対する異なる見方と答えだ。「ゆれながら咲く花」はそれが“時代”だと答える。「クラスの子たちが全員、3年生になるようにすることです。子どもたちの成績を上げることも、子どもたちの人生の責任を取ることもできないけど、私が担任を務めた子どもたちを全員、そのまま次の担任の先生に引き渡すこと、それが私が担任として望むことです」。成績も人生も責任を取ることができないというチョン・インジェのこの言葉は、一瞬、無力に見えるが、もしかしたら「ゆれながら咲く花」が見つめる、そして、今の教師と学校が生徒たちにできるベスト以上のことなのかもしれない。
しかし、時には質問を投げるだけでは足りない。「ゆれながら咲く花」が珍しくちゃんとした質問を投げた理由は、成長痛と思い込んでしまうには、大人になっていく過程であまりにも苦しむこのかわいそうな子どもたちを、これ以上放っておくことができなかったためではないのか。だから、重要なのは「学校はどんな場所なのか」に対する異なる見方と答えだ。「ゆれながら咲く花」はそれが“時代”だと答える。「クラスの子たちが全員、3年生になるようにすることです。子どもたちの成績を上げることも、子どもたちの人生の責任を取ることもできないけど、私が担任を務めた子どもたちを全員、そのまま次の担任の先生に引き渡すこと、それが私が担任として望むことです」。成績も人生も責任を取ることができないというチョン・インジェのこの言葉は、一瞬、無力に見えるが、もしかしたら「ゆれながら咲く花」が見つめる、そして、今の教師と学校が生徒たちにできるベスト以上のことなのかもしれない。
高校2年生、18歳。生徒たちのこの時期を、大学と社会に受け入れてもらうため喜んで生贄に捧げる無名の時間ではなく、ありのまま生きて笑って彷徨って悟るべき人生の大切な時期として認めることから問題解決への糸口を探してみよう。教師と保護者、社会の大人たちが学校を通じてやるべきことは、チョン・インジェのように子どもたちのその時期を守り、次の時期へ導くことである。「生まれた時から20歳だったらいいな」と言う生徒に、今の君の18歳は耐えたり諦めながら暮らす時間ではないと、学校は大学や社会に出るために通過するだけの空間ではないと言ってあげることだ。
床に転がった椅子は、無力な公教育と教権であり、教師になったばかりの先生が抱いた情熱であり、平凡な保護者が望んだ期待である。そして、夢見る時期を奪われた子どもたちそのものだ。耐えてもいい時期なんてない。それに、今だけを耐えればよりいい明日が来るとも言えない世の中じゃないのか。時代が変わったことも、現実が大変なことも事実だ。そのため、より念入りに見て、より長く見なければならない。それが今を耐えた後、社会に出てから会う世の中を“より悪くなることはあっても、よくなることは一つもない”場所にした大人たちが喜んで負うべき責任である。
学校という 収容所で衝突する欲望

まず、四角い教室の中にいる様々な生徒たちを見てみよう。勉強ができる生徒とその子を嫉妬する生徒、当たり前のように遅刻し平然と授業をサボる生徒、学校には毎日欠かさず来るが勉強する代わりに昨夜取れなかった睡眠を取る生徒、授業時間にはまるで死んでいるように見えるが休み時間には生き生きとする生徒などがいる。何より、勉強は嫌いだが大学には行きたいと思う大多数の生徒がいるのだ。隣の席に並んで座ることなく、一人ずつ座っているこの子たちは、同じクラスの友だちに淡い恋心を抱く前に、目に見えたり見えなかったりする序列の中で自分たちの位置を確認し、嫉妬と劣等感を先に学ぶ。この子たちにとって学校とは、大学という生徒たちにとって共通の恐怖に支配されたまま、それぞれの方法で耐えなければならない収容所だ。
教師たちも彼らとあまり変わらない。「まだ……子どもたちの手を離す時ではない……」と自分自身に言い聞かせながら、生徒たちの手を自分の手で叩くチョン・インジェ(チャン・ナラ)は、些細な出来事一つで地位が揺れてしまう臨時教師だ。現実を静観したり冷笑したり、現実に安住したり対抗したいと思う教師たちにとって、学校は無力感と戦わなければならない組織だ。そして、保護者たちにとって学校は、自分の子どもが大学に進学するにおいて少なくとも邪魔にはなっていけない組織であり、子どもを通して投影された自分のアイデンティティーを確認する場所だ。このように、誰かにとっては監獄であり、誰かにとっては仕事である学校は、どの組織や空間よりも様々な面を持った人々が一緒に集まっており、一つに融合できない欲望が衝突する場所だ。
そして“ソウル市内の高校178校のうち、149位である”江北(カンブク)の高校という明確な地域性と序列を明かしたうえでスタートした「ゆれながら咲く花」のもっとも大きな美徳は、この欲望の激しい衝突を深く覗き込んで、思慮深く描き出すという点だ。授業中、一つのチームになったわずか5~6人の子どもたちの間でも、お互いに望むことがはっきりと違う。まして、一つのクラスに集まったおよそ30人の子どもたちも、授業の方向を一つに決めることができない。成績が悪くて迷う子どもたちと成長の過程で迷っている子どもたちのうち、どちらのほうが大切ではないと断言できるのか。家庭でちゃんと育てられなかったオ・ジョンホ(クァク・ジョンウク)が教室の中で見せる未熟で荒い人情の闘争も、子どもたちが眠らない授業をしたいと思うチョン・インジェの理想も、将来を左右する自分の子どもの成績が学校の目的でならなければならないと信じるミンギの母(キム・ナウン)の望みも、その人々にとってはそれぞれ正当な欲望である。
「ゆれながら咲く花」は質問を投げかけるドラマだ。このドラマは、学校内の当事者たちが提示する問題のうち、どれが正しくてどれが間違っていると判断することはせず、愚かな楽観主義や性急な代案で包むのでもなく、まず各主体たちの欲望を覗き込んでいる。それはじっくりと見てこそ気づくことができ、長く見てこそ理解できるような質問を投げていることになる。知的障害を持つ生徒ハン・ヨンウ(キム・チャンファン)と問題児オ・ジョンホの衝突をヨンウを転学させるための理由にしようとする学校に向かって、「学校とオ・ジョンホ、何が違いますか?」と聞く。模範答案の通りに書いた論述の答案でも高い点数をあげることができないという教師に向かって、「それでは、模範答案はどうして存在するんですか?」と聞く。
子どもたちのある時期を守るということ

高校2年生、18歳。生徒たちのこの時期を、大学と社会に受け入れてもらうため喜んで生贄に捧げる無名の時間ではなく、ありのまま生きて笑って彷徨って悟るべき人生の大切な時期として認めることから問題解決への糸口を探してみよう。教師と保護者、社会の大人たちが学校を通じてやるべきことは、チョン・インジェのように子どもたちのその時期を守り、次の時期へ導くことである。「生まれた時から20歳だったらいいな」と言う生徒に、今の君の18歳は耐えたり諦めながら暮らす時間ではないと、学校は大学や社会に出るために通過するだけの空間ではないと言ってあげることだ。
床に転がった椅子は、無力な公教育と教権であり、教師になったばかりの先生が抱いた情熱であり、平凡な保護者が望んだ期待である。そして、夢見る時期を奪われた子どもたちそのものだ。耐えてもいい時期なんてない。それに、今だけを耐えればよりいい明日が来るとも言えない世の中じゃないのか。時代が変わったことも、現実が大変なことも事実だ。そのため、より念入りに見て、より長く見なければならない。それが今を耐えた後、社会に出てから会う世の中を“より悪くなることはあっても、よくなることは一つもない”場所にした大人たちが喜んで負うべき責任である。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- キム・ヒジュ、編集 : イ・ジヘ、翻訳 : ナ・ウンジョン
topics