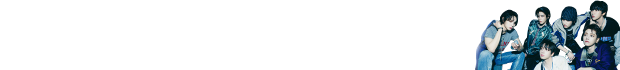映画会社チョンオラム「VPF利用料を支払う義務はない」と訴訟提起
 写真=映画会社チョンオラム
写真=映画会社チョンオラム韓国映画祭作家協会は16日、「会員である映画会社チョンオラムが、ディシネマ・オブ・コリア(以下DCK)を相手取り、映画配給会社のデジタル上映システム利用料の請求における債務不存在確認請求の訴訟を10月1日に提起した」と明らかにした。
この訴訟は、映画会社チョンオラムがDCKと締結したデジタルシネマ利用契約が、公正取引法に反する契約だったため、これによるデジタルフィルム上映におけるシステム利用料、つまりVPFを支給する義務がないことを確認する訴訟である。これに関連して、映画会社チョンオラムは今月4日、公正取引委員会に不公正取引行為の申告書を提出した。
映画会社チョンオラムによると、昨年11月に映画「26年」を配給するため、ロッテショッピング・ロッテシネマ(以下ロッテシネマ)、CJ CGVと映画の上映契約を締結した。その後、ロッテシネマとCJ CGVが合弁して設立したDCKから、各上映館内に設置されたデジタルフィルム上映におけるシステム利用料であるVPFを支給しなければならないという内容の「デジタルシネマ利用契約」の締結を要請された。
映画会社側は、映画上映における契約上、デジタルフィルム上映の委託がロッテシネマやCJ CGVの義務であり、ランドシネマやアートレオンなど、18の映画館はVPFを上映館が負担しているという理由で、この要請を拒否した。すると、「26年」の封切り(2012年11月29日)1週間を目前にして、ロッテシネマとCJ CGV上映館の(前売り)予約サービスが開始されず、これを受けてデジタルシネマの利用契約を締結した後、上映館の予約サービスがすぐに開始されたと説明した。
映画会社チョンオラム側は、今回の訴訟について「DCKとのデジタルシネマ利用における契約は、不公正な状況で結ばれた不公正な契約であるため、公正取引法を違反したものだ」とし、「民法第103条によると、無効な契約による利用料は支払う義務がない」と主張した。
韓国映画祭作家協会は、2012年の映画振興委員会の産業統計資料によると、今回の訴訟の対象であるロッテシネマとCJ CGVの総スクリーンと座席数のシェアは約70%に達し、70%の占有率を持った両社が共同出資して設立したDCKは、両社の子会社という点について言及し、「彼らが配給会社にデジタルフィルム上映のシステム費用を負担させる場合、配給会社は他の選択をすることができないし、彼らが提示する条件をそのまま受け入れるしかない。これは公正取引法で規定する強制取引と地位を利用した不当取引に該当する」と指摘した。
また「DCKが取引上の地位を利用して、配給会社にデジタルシネマ利用の契約を締結させる目的は、まさにVPFを徴収するためだ」と、映画会社チョンオラム側に力を加えた。
協会側によると、2007年11月にCJ CGVとロッテシネマはそれぞれ50%の持分を投資してDCKを設立した。DCKは2009年末までにVPFモデルを適用して、約1,000にのぼるデジタルシネマシステムの構築計画を立てた。VPFモデルは、劇場が初期設備費用の3分の1を負担して、10年間にわたる維持管理費をDCKに納付すれば、10年後に装備の所有権を劇場に移転することにしており、DCKは初期設備にかかった残りの費用を補充するために、配給会社から映画公開時に上映館1館にあたり80万ウォン(約7万4千円)のVPFを徴収してきた。
協会側は、デジタル上映機器がその場かぎりの消耗品ではなく、フィルムでの上映時より運営要員及び管理費用が削減され、CMの効率的な配分により広告の売り上げが増加したにもかかわらず、VPFを制作会社と配給会社に請求することは不当だと説明した。
最後に「今回の訴訟は、何よりも映画の公開を担保に有利な地位を利用して、劇場設備の費用を制作費に転嫁するという、大企業の独断的な行動に対する問題提起だとみられる。取引上、優越した地位を利用して、大手子会社であるDCKが不公正に制作会社と配給会社に請求しているVPFが果たして正当な金額であるのか、これに対する公正な議論が行われることを望んでいる」と、VPF支給の正当性の有無についての議論を促した。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- キム・ミリ
topics