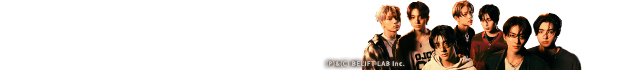イ・ラン「見せてと言われて、すべてを見せるつもりはない」
イ・ランは理解できない曲を歌う。しかし、それを責めたり変えようとはしない。ただ、冗談でも言おうとしながら歌を歌い出す。きれいな修飾語など付けず、言い放つその優しい言葉を人々が誤解せず聞くことができるなら、たとえ見た目が冗談であろうが本音であろうが、別に関係ないと思う。イ・ランの初フルアルバム「ヨンヨンスン」はそういう疑問を直観的に掘り下げている。本名もイ・ランで、電源コードを抜いたら電源が切れてしまう2006年に買ったMacBookの内蔵マイクを使い、一人で音楽を録音した。そして、事務所側がマスタリングだけ行い、このアルバムが生まれた。イ・ランはこのアルバムで隠された意味を把握させたりもう一度考えさせたりしない。頭の中に浮かぶことをすべてそのまま外に出した後、気に入らない言葉を自分で選んで消す過程を通じて歌詞を書くという彼女ならではの作業方法は、イ・ランの音楽が彼女独特の雰囲気を持つ理由を確実に見せてくれる。アルバム発売後、公演を行い始めてから友だちのへミとドラマーのインチョルが合流し、3人組のバンドになったイ・ランに会った。イ・ランはよく冗談を言った。そして、その中には緩いけれど鮮やかな本音が隠されていた。
―イ・ランが描いた「イ・ラン歴史漫画」を見たら、「ヨンヨンスン」を持っている自分の後ろに星をたくさん描いてあったが。イ・ラン:実際は……別に感動はなかった。
ヘミ:私は私のアルバムではないので別に……。
イ・ラン:ヘミもインチョルもアルバム作業の後から合流したので、アルバムには参加しなかった。ジャケットを作る時は話し合ったけど。2人はただ私のアルバムが無事に(笑) リリースされるように、私のそばで手伝ってくれた。
―人生で初のフルアルバムなのに、なぜそんなに平然としていたのか。
イ・ラン:事務所と会議してからアルバムが出るまで、およそ1年8ヶ月かかった。私的にはアルバムに入る予定の音楽をすべて事務所に渡したので、1ヶ月後にはアルバムが完成すると思った。でも、他にもしなければならないことがたくさんあった。社長はとても几帳面に仕事をこなす方で、イ・ランというミュージシャンをちゃんと見せたいと思っていたようだ。面白いミュージシャンではなく、妖精でもないような。結果的に満足している。でも、私が音楽を手放した後からも準備が長くなったので、途中からはアルバムに対する愛着がなくなってしまった。「別に出ても出なくてもいいや」というような感じだった(笑)
「アイドルの曲をカバーしてみたい」

イ・ラン:ぴったり合っていると思う。そして、何より重要なのは、もし私が一人でアルバムを作ったら、弘大(ホンデ)のフリーマーケットのようなところで、何枚か売って終わったと思う(笑)
―アルバムを出した後にメンバーたちを集めたことが独特だが。
イ・ラン:次第に公演を行うことになって、一人で公演をやるのが面白くなかった。ステージのすべての空間に対して一人で責任を取らなければならないから、それが負担になった。でも、誰か一人だけでも私のそばにいてくれると、私はまったく緊張しないタイプだ。そして、今、私たちは3人だから、より緊張しなくなった。最初、ヘミに話をしたら、とても喜んで「わ!いいよ!面白そうじゃん!」と言ってくれて、一緒にやることが決まった。ヘミはとても練習熱心で、一人で聞いて思ったことをいつも練習してくる。以前、一人でレコーディングをした時は、コーラスも一人で歌いながらやったけど、今は3人で一緒に公演をしていて、隣で色んなサウンドを具現化してくれるので、とても満足している。
―インチョルは他のバンドの活動をやっている途中で、合流の提案を受けたと聞いたが。
インチョル:そうだ。初めてセッションしに行った時はかなり心配だった。イ・ランの音楽が非常に異質であるため難しく感じられた。僕なりにたくさん聞いてコピーや構想もしてみたが、どんなふうに演奏すればいいか、その感覚がまったくつかめなかった。ドラムを最初から最後まで同じように叩いたら面白くないので少しずつ変えなければならないが、最初はどこから手をつければいいかピンと来なかった。ドラマーの立場としてはほぼ新しいものを演奏する状態だった。今はドラマーとしての僕の領域を徐々に広めていく過程だと思っている。
―一緒に公演を準備しながらお互いに音楽的に影響を受けたり、与えたりもしているのか。
イ・ラン:3人で一緒に曲を作ったことはないので、音楽においてはまだ直接的に影響を受けたり与えたりはしていないと思う。
―曲の制作作業を一緒にしていないため、心配になる部分はないのか。
インチョル:日本での公演に一緒に行って、アルバムが出るまで準備をする中で、イ・ランというバンドならではの色を少しず持つようになった。そして、それはメンバーそれぞれが違うことをやっている部分から成り立つという点が面白い。ヘミはヘミなりに家具を作る仕事をしていて、イ・ランはイ・ランなりに絵を描いたり、曲を書いたり、映画を作っている。私の場合は違うバンドの活動もやっている。このようなことすべてがバンドとしてイ・ランならではのカラーを作り上げているのだと思う。
ヘミ:私が思うには、これからもこのようにやっていくと思う。イ・ランの音楽は誰のものでもなく、イ・ラン自身のものだから。曲の作業に私とインチョルが加わったら違う音楽ができるかもしれないけど、私たちはそれを望んではいない。今のままがいいと思う。公演を間近に控えて「こんなふうにやってみたらどう?」と意見を出したりするけど、イ・ランの音楽の骨格には触れたりしない。私たちが加わることで音楽を満たせる感じを与える程度が一番いいと思う。
―イ・ランがアイドルの曲をカバーしてみたいという話をしたが。
ヘミ:……。
インチョル:……アイドル?
イ・ラン:ハハハ。メンバーたちが同意しないんだったら、私もやるつもりはない。家で一人でやればいいから(笑) 2NE1の曲とかはコード表を探して一人でも楽しく歌っている(笑) 新曲の「I LOVE YOU」が好きだけど、コードがとても難しかった。
「理解できないものを歌にする」

イ・ラン:2006年にギターを初めて握った。ギターのコードを覚えていないまま、手の形だけ一つずつ習った。2つの手の形を知るようになって、その2つを繋げて出る音を使って色んなものを弾いてみた。少しずつ知っていく楽しさを原動力にして学び続けることができたと思う。だから、今は基本コードをすべて知っている。A、B、C、D、E、F、Gまで。でも、その次からが難しいと思い始めた。手を横方向に動かさなければならない(笑) その時からはあまり詳しく知りたくなくなった。
ヘミ:衝撃的な発言だ。これをヘッドラインに使ってください(笑) 「イ・ラン、A、B、C、D、E、F、Gコード以外は気にしていない」
イ・ラン:難しいもん(笑) 手をネックのボディ側に移して掴むことを私の頭は望んでいないと思う。やってみようと思ってコード表を見たり周りの人に教えてもらったりしたけど、あまり手が動かない。多分、横たわって曲を作る時、ギターを弾くにはネックのヘッド側を掴んだ方が弾きやすいからだと思う。難しいことはあまりしない。
―いつかネックのボディ側の音を出したいと思う時が来ると思う。
イ・ラン:あ、もちろんそう思う時もある。でも、そうなってもやっている途中で、結局諦めてしまう。一度、やってみようと運指を探したことがあるけど、ボディ側に入ったらよく分からなくなって……諦めた(笑)
インチョル:でも、Fコードのようなコードを掴む時はちゃんとしたい。難しいのは分かるけど、音がちゃんと出ていないので……。
―アルバムの話をしよう。デモ版ではあるが計画通り外部の音が一緒に録音されていた。
イ・ラン:普段、私は雑音が混ざった状態の音に慣れている。そのため、曲を作る時もその方が気楽に感じる。映画音楽の作業をする時も静かな状態とか台詞がきれいに聞こえる状態でやったら、本当に狂ってしまいそうになる。それで、わざと雑音を入れる。きれいに同時録音をしたものの上に、アフターレコーディングをして雑音を入れる。デモ曲もわざと窓を開けて作業したこともあり、通り過ぎる車の音のようなものが入るようにした。これは、聞く時も同じ。きれいな曲を聞いたら拒否感を感じる。
―「ピイピイ」に入れたイルカの鳴き声も印象的だった。曲自体を一つのイメージとして見て、音を再現するのか。
イ・ラン:「ピイピイ」はイルカの虐殺に関する映画を見て作った曲。イルカがかわいそうだと思って曲を作りながら映画に出るイルカの鳴き声を入れた。他の曲の場合は、ただ聞こえる音を入れている。ギターやボーカルをレコーディングしたら、その時また、他の音が聞こえてくるので、それを再現しようとしながら入れるのだ。「おかしなこと」に出る「パンパバン バババン」のような音も、ただ私に聞こえる音だったので入れた。
―イ・ランの音楽が好きな人々は、語っているように書いた歌詞にとても共感している。
イ・ラン:曲を書いた時は人々と共感することを考えていなかった。でも、アルバムをリリースするようになってからは、人々に本当にこの曲を聞いてほしかった。私は日記を文章で書く時もあるし、パソコンに書き込む時もあるし、歌で歌う時もある。そんな中、歌で歌う時に出たものがこの曲たちである。「君のリズム」の場合も、何時間もギターを弾きながらただぶつぶつと言葉を吐き出した。その後、これはあまり好きじゃないとか、これは気に入らない、と思いながら選んでいくうちに歌詞がまとまった。
―結局、「ヨンヨンスン」はどんなことが話したかったのか。
イ・ラン:世の中のことで、理解できない部分がある。私はその理解できないことを歌、映画、絵、文章で表現している。「ヨンヨンスン」も同じだ。
―理解できないことを変えたいと思ったりもするのか。
イ・ラン:それは違う。ただ私のような人が聞いたら好きなんじゃないかなと思った。私は、人間は変わらないと思うタイプである。その代わりにその変わらないことを少しひねって、「これ、笑えるよね」と言っているだけである。例えば、映画にしたら、その映画を気に入る人が100人しかいないとしても、その100人が一緒に楽しむことができたら、それでいいと思うことであり、音楽も同じである。「こんなふうに考えている人々が一緒に共感できたらいいな、反応してくれたらいいな」と思った。「君のリズム」はある友だちのために作った曲だ。年を重ねるにつれ、その友達がだんだん変わり遠ざかっていくような感じがして、悲しくなった。こういう気持ちなら他の人々と共感することができると思った。
「これからも音楽を続けるかどうかは分からない」

イ・ラン:そう。ハハ。繋げることが非常に好き。だから、このアルバムにあるものが、その映画にもあったりする。本当にずいぶん前から鴨が好きだった。でも、なぜ好きになったのかよく分からない。ただ、いつからか好きになっていた。私が続けて何かを繋げているということを象徴的に見せてくれるシンボルなのかもしれない。幼い時に自分で撮った映像から、いつか私が最後に撮影する映画が完成し、そのすべての過程の中に、私が向かっている方向が見えたらいいなと思う。何かが好きで、続けてその方向へ向かっているということを。
―鴨のアイテムを買い集めているのか。
イ・ラン:ただ描いている。私は浪費をあまりしない。好きなものがあったら、自分で作るタイプ。曲を作ったり、歌詞を書いたり、絵を描いたりする。鴨が好きなら、鴨を描けばいいと思う(笑) ミニアルバムのジャケットにある鴨の本は、鴨が好きな私のために知り合いがプレゼントしてくれたもの。幼い頃、H.O.T.が好きだったけど、彼らの家まで追っかけたりはしなかった。代わりに、家でただH.O.T.のチャン・ウヒョクに出会い、彼と付き合うようになるまでのストーリーをひたすら想像した(笑) ノートに書いたりもしたし。BIGBANGのSOLも好きだ。それで、SOLと電話するシチュエーションを一人で演じたりする。「あら、SOL!うん、うん。今日、飲みに行こうか?」みたいな(笑)
―「ヨンヨンスン」を聞いていたら、「ヨンヨンスン」以後のイ・ランが知りたくなる。
イ・ラン:実は、これからのことは自分でもよく分からない。以前、音楽をたくさん作っておくことができたのは、余った時間が多かったためである。一人で寂しかったり悲しかったりする時、もしくはやることがないのに時間だけたくさん余っている時に音楽を作った。でも、今はそういう時間があまりない。私は映画監督になりたいし、シナリオも書きたい。今も悲しかったり寂しかったりなかなか眠れない時は、歌を歌うけれど、そういう時間が以前ほど多くはない。以前は毎晩のように歌を歌い、曲を作ったので、1ヶ月ほどの期間で曲をたくさん作り出すことができた。でも、これからのことは本当によく分からない。
―インタビューしたり、ショーケースを準備しているように、イ・ランを世の中に知らせていると思う。
イ・ラン:もし上手くいくとしても、興奮してそのまま走り続けることはたぶんないと思う。「見せて、見せて!」と言われたからといって、「分かりました!全部お見せします!」とは言わないと思う。日本公演に行った時の気持ちくらい準備してやれたら、ちょうどいいかなと思う。その時、私は本当に幸せだった。指折り数えて待ったことが幸せだった。
―これまでイ・ランは神から独立的な存在だった。でも、これからはその中に何かを挿入することも可能だと思う。
イ・ラン:もし、そうなるとしたら、私はやめると思う。昔、やっていた通りに、一人で作業して友達に聞かせたり、見せたりする形に戻ると思う。私はよく諦めるし、よく逃げる。だから、少し辛いと思ったら、自分がいた場所に戻って一人で自分の曲を聞きながら癒された方がいいと思う。「SUPER STAR K」で挑戦者たちがステージに上がる時、緊張感をなくすため「私はできる!」と叫ぶ姿をよく見かける。もちろん、それと似ているような気持ちが私たちにもある。それで、「うまくやろう」と思ってからステージに立ったりするけれど、もしそれがその挑戦者たちのように心から引き出せない覚悟だったら、それは自分の仕事ではないと思う。だからしない方がいいと思う。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- イ・ギョンジン、インタビュー : ファン・ヒョジン、写真 : イ・ジンヒョク、翻訳 : ナ・ウンジョン
topics