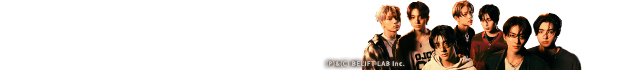「オフィス」ペ・ソンウ“殺人よりも未来が与える漠然さが本当の恐怖”

映画「オフィス」(監督:ホン・ウォンチャン、制作:花)も同じだ。平凡な家長であったが、自身の家族を殺害し、また会社に出勤するキム・ビョングク課長を演じたペ・ソンウは、息苦しい人生の重さに耐えなければならないサラリーマンと殺人鬼の間を絶妙に行き来し、観客にゾッとする恐怖を与えた。
ペ・ソンウは自身が演じたキム・ビョングク課長を思い出すと悲しいと話した。来月のクレジットカードの請求書や生活の心配のほうが殺人事件より怖くないかと。見えない未来が与える漠然さこそ恐怖ではないかと。
大学路(テハンノ)の演劇舞台から始め、数多くの作品のエキストラと助演を経ていつの間にか主演レベルの俳優にまで成長した彼は「幸福指数は高くなったが、依然不安だ」と話した。常に選択を受ける立場にある俳優の人生から来る必然的な悩みであろう。
「『オフィス』を撮ってからもう少し大きな役、作品を率いる役を演じてみたくなりました。プレッシャーなしで楽な役を演じるのもいいですが、似たような出番の似たようなキャラクターを引き続き演じていると、いつの間にか消耗されます。周りではそのようなところを心配していました。単に出番の問題ではなく、作品に深く関わるキャラクターに挑戦したいです。10月に公開される映画『リバイバル 妻は二度殺される』『造られた殺人』がそのような作品です」

―「オフィス」に「ビューティー・インサイド」「ベテラン」まで。言葉通りの全盛期だ。デビュー以来最高の全盛期だ。周りの反応が変わったのを感じているか。
ペ・ソンウ:全盛期というよりは、全盛期間近とも言えようか(笑) 「私の愛、私の花嫁」の時も近所の住民たちが喜んだ。
―メディア向けの試写会として、異例的に(?)悲鳴が上がったりしたが。
ペ・ソンウ:本当だ。血まみれになったり、すごく厳しいシーンが出てくるわけでもないのにすごく驚いているようだった。
―シナリオの感じはどうだったか。
ペ・ソンウ:とてもゴージャスな感じだった!もちろん短所もあった。スリラーに包装されたホラーではないか。スリラーは論理的に展開すべきなのにホラージャンル特有の超自然な要素が入っていて、論理的に展開することができない部分ができた。あまりにも無責任なのではと懸念した。それでも止める理由がないほど完成度の高いシナリオだった。出番そのものが多いわけではなかったが、映画全体を貫通するキャラクターなのでぜひ演じたかった。

ペ・ソンウ:そうだ。これまで俳優は“トーン”で勝負したらいけないと思っていた。技術的にトーンを変えるよりは、情緒的にアプローチしたほうがいいと思っていた。演技のトーンをわざわざ変えるというのは言葉通り“演技をする”ことになるから。演劇をしていた頃から、情緒的なアプローチが一番効果的だと思っていた。けど、今回のキム・ビョングク課長はこれまで僕が演じてきた悪役の演技とは少し異なる人物であった。殺人鬼だが、僕には悲しく感じられた。共感もすごくできた。殺人という行為に対する共感ではなく、彼が抱いていたと思うその情緒に共感した。
―例えば?
ペ・ソンウ:小道具であった家族写真を撮る時にすごく悲しかった。キム・ビョングク課長は日常が疲れている人だ。年に1回の少しの休息である家族旅行でもただ幸せであるようには見えなかった。社会で基盤を整えて普遍的な人生を生きる人も、常に生活の心配をするではないか。いつまでこんな生活をするんだろう。今後どれほど仕事を続けることができるだろう。こんな悩みが最も大きな悲劇、最も大きな恐怖ではないだろうか。そんな点で共感できた。殺人事件も怖いけど、直面した明日が不安なのが本当の恐怖だ。
―情緒に対する共感が演技のトーンを変えたのか。
ペ・ソンウ:ある程度はそうだ。ジャンル的な特性上、基本的に見せるべき恐怖の演技が必要だった。だとすると、どのようにして観客を怖くするか。登場の度に人をちぎって殺すわけにはいかないだろう。僕は「オフィス」を、オフィスに悪魔が取り付いた物語だと見た。その悪魔が最も弱い人、だからキム・ビョングク課長に入ってきたのだ。その中のストレス、人生の疲労、悲しみをベースに置いて演じた。
―社会生活は上手なほうか。
ペ・ソンウ:少し人見知りなほうだ。特に先輩に接するのが難しい。機嫌もかなり伺うほうだ。それでも現場ではコミュニケーションをしようと努力している。実際、人見知りでない人はいないと思う。みんなある程度はそんな部分があるのではないか。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- キム・スジョン、写真 : ムン・スジ
topics