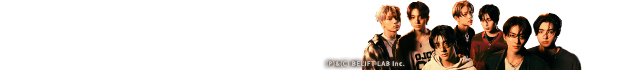コン・ヒョジンがおすすめする「私をときめかせる映画」

そのようなコン・ヒョジンが映画「ブーメラン・ファミリー」では、“結婚の乗り換え専門”、それも中学生の娘を持つバツイチ女性のミヨンを演じる。母親の役は、MBCドラマ「ありがとうございます」と映画「今、このままがいい」以来3度目である。「イメージに対するプレッシャーはありません。むしろ、人々が私のことを“子持ちの母親だと勘違いしてもらっては困る”という考えの方が先にあります。それに厳密に言うと、私が母親の深い愛情を演じた作品は『ありがとうございます』だけです。『今、このままがいい』もそうだし、今回の作品も“母親”というのはキャラクターが持つ設定であるだけです。母親に見えないお母さんかな?」
コン・ヒョジンはミヨンの役を演じながら、何度も痛快さを感じたようだった。「演奏がぴったり合った時に感じる快感のようなものがありますよね?今回の作品を撮影しながらそれを感じました。家族同士で喧嘩するシーンが多く、あちこちで火花が飛び散りました」と“家族崩壊”について興奮気味に紹介していたコン・ヒョジンが「自分をときめかせる映画」をおすすめしてくれた。

2013年/ジョー・ライト
「劇場で見る前に、先に機内で見た映画です。見た瞬間、魅了されました。演劇的な舞台転換とミュージカル方式を使ったビジュアルが本当に良かったです。大邸宅で出会ったアンナ・カレーニナ(キーラ・ナイトレイ)とヴロンスキー(アーロン・テイラー=ジョンソン)がドアを開けて中へ入ると、舞台がレストランに変わるというような舞台転換に驚きました。人物の動線や感情によって絶妙に変わる舞台がとても魅力的でした。是非、DVDで所蔵したい映画です」
ロシアが生んだ大文豪レフ・トルストイとイギリスのラブコメディの名門ワーキング・タイトル・フィルムズがコラボレーションした作品である。今まで何度もリメイクされた小説「アンナ・カレーニナ」を再び映画として生み出したのは、「つぐない」「プライドと偏見」のジョー・ライト監督である。ジョー・ライトの「アンナ・カレーニナ」が、今までのリメイク作と違う点は物語の伝達方法にある。演劇の要素を加えたこの映画は、見る間ずっと現実と幻想を行き来するような錯覚を呼び起こす。グレタ・ガルボ、ヴィヴィアン・リー、ソフィー・マルソーなど、当代最高の女優たちが演じたアンナ・カレーニナをキーラ・ナイトレイが演じた。

2012年/リン・ラムジー
「『少年は残酷な弓を射る』もメゾンセン(mise en scene:舞台の上での登場人物の配置や役割、舞台装置、照明などの総合的な計画)が際立つ作品です。ティルダ・スウィントンが出演した映画だったので見ましたが、見た後はビジュアルにより惹かれました。望んでいない妊娠によって母親になったエヴァ(ティルダ・スウィントン)の恐怖と罪悪感などを“赤い色”で視覚化していますが、色使いが映画にぴったりでした。エヴァが赤い壁を背景にじっと座っている静的なシーンもとても綺麗でした。」
英国女性作家文学賞の最高峰・オレンジ賞を受賞したライオネル・シュライバーの小説を原作とした映画。高校で起きた残酷な犯罪を描いたという点で、ガス・ヴァン・サント監督の「エレファント」と崇高な母性神話を解体したという点でポン・ジュノ監督の「母なる証明」が浮かび上がる。問題作「ボクと空と麦畑」でデビューしたスコットランド出身の女流監督リン・ラムジーの繊細ながらも挑発的な演出が見る人の胸を締めつける。罪悪感や喪失感、不安などの複雑な感情を緻密かつ適切に描き出したティルダ・スウィントンの演技は実に圧巻である。ケヴィンという悪魔のような人物を恐ろしく演じきった新人エズラ・ミラーの演技も驚くべきものだ。

2012年/サラー・ポーリー
「愛はみんな同じだと思います。キラキラ輝いていた愛も、時間が経てば冷えてしまい、お互いが新しい愛を求めてそれぞれの道へと歩むが、新しく芽生えた愛も結局は倦怠期を迎えることになります。『テイク・ディス・ワルツ』は、長い時間付き合ってきた恋人にとっては苦々しい映画です。だけど、苦々しいストーリーとは違って、ビジュアルはとても感性的で、衣装や色使いもとても綺麗でした。演出も面白かったのですが、女性主人公のマーゴ(ミシェル・ウィリアムズ)が音楽に酔って遊園地の乗り物に乗っていたシーンが特に記憶に残っています。乗り物が止まり、明かりがついた瞬間、マーゴの精神も現実へと戻って来るのですが、その瞬間を絶妙に表現しています。そのような部分が興味深かったです」
愛とは、“始まりと共に別れに向かって走り出す期限付きの感情”と定めると、悲しすぎるだろうか。「テイク・ディス・ワルツ」は、キラキラと輝いていた愛が消滅する過程を淡々としながらも繊細に描いた映画だ。倦怠期に陥った結婚5年目の主婦マーゴに訪れた新しい愛。しかし、新しいものもいつかは古いものとなるように、永遠だと思っていた新たな恋人との愛も次第に光を失っていく。前作「アウェイ・フロム・ハー 君を想う」で愛に対する深い洞察を見せてくれたサラー・ポーリー監督の2度目の演出作である。

2012年/マリク・ベンジェルール
「とても暖かい映画です。音楽の力を改めて感じさせてくれる映画でもあります。音楽と物語がよく調和していますが、実話だという点から来る感動も大きかったです。映画を見て、言葉では説明できないような感情がこみ上げてきたことを思い出します」
1970年代、人種差別がピークに達した南アフリカ共和国。閉鎖的なこの国にロドリゲスという歌手の名前が書かれたアメリカのアルバムが1枚流れ込んでくる。体制に対する抵抗的なメッセージがびっしり詰まっているこのアルバムは、自由を求めていた若者たちの心を動かし、抵抗運動の起爆剤となる。そうしてロドリゲスは南アフリカでビートルズに負けない大スターになった。しかし、彼の正体を誰も知らなかった。映画はたった2枚のアルバムを残して消えたロドリゲスの痕跡を辿る過程を描いている。「第85回アカデミー賞」で長編ドキュメンタリー賞を受賞した作品である。

2013年/パク・チャヌク
「映画を見ていて思わず『うわっ』と叫ぶ時があります。例えば、素晴らしいキャラクターに出会った時です。『イノセント・ガーデン』がそうでした。見ている間、映画の中の二人の女性主人公のミア・ワシコウスカとニコール・キッドマンが本当に羨ましかったです。『演技をしながら、本当に楽しかっただろうな』と女優としての嫉妬を感じました。すでに完成した映画なので、私が演じることはできないという事実が悲しいだけです」
パク・チャヌク監督のハリウッド進出作。「プリズン・ブレイク」のウェントワース・ミラーがシナリオを書いたことで話題になった。「イノセント・ガーデン」には、アルフレッド・ヒッチコックの「疑惑の影」(1943)の影がいくつか見えるが、これはパク・チャヌクではなくウェントワース・ミラーによる影響である。パク・チャヌクは、「アルフレッド・ヒッチコックにオマージュを捧げるウェントワース・ミラーのシナリオで、むしろアルフレッド・ヒッチコックの軌跡を消そうとした」とインタビューで明かした。実際にパク・チャヌク監督が手がけた「イノセント・カーデン」は、「疑惑の影」よりパク・チャヌク監督の前作と肩を並べるほどの作品として誕生した。間違いなくパク・チャヌク監督独自のスタイルの映画だ。

人々が簡単に思い浮かべるコン・ヒョジンは、クールで華やかなイメージのファッションリーダーだ。だが、彼女が出版した環境書籍「コンチェク(コンノート)」を見ると、コン・ヒョジンは一人だけの静的な時間も最高に楽しめる人だということが分かる。コン・ヒョジンは、以前から環境を守ることのできる小さな習慣を続けている。「自分だけではなく、自分の周りにある様々な生命体に興味があります。動物であれ、植物であれ、それらを認知して配慮しながら生きる人生も素晴らしいということをゆっくり伝えていきたいです。私が守り続けている小さな配慮が誰かの人生に影響を与えることもあるかもしれません。だからこそ、出来る限り良い影響を与えたいんです」
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- チョン・シウ、写真 : イ・ジンヒョク、編集 : ホン・ジユ、翻訳 : チェ・ユンジョン
topics