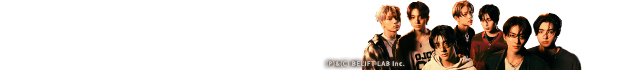【映画レビュー】「弁護人」拝金主義から人権弁護士への変化、ソン・ガンホが巧みに演じた
 写真=ウィダスフィルム
写真=ウィダスフィルム先に断っておくが、「弁護人」は故ノ・ムヒョン大統領の政治的足跡を辿る映画ではない。この映画の中には政治的に偏った立場や主張などは盛り込まれていない。ただ一般的な常識では納得し難い事件に憤る人間ノ・ムヒョン、市民ノ・ムヒョン、弁護士ノ・ムヒョンが描かれているだけだ。80年代を背景にしているだけに、その時代の歪んだ権力、乱れた社会的背景を避けては通れない。しかし、背景は言葉通りただの背景であり、この映画はソン・ウソクという人物が激動の時代を通して得た省察がメインだ。故ノ・ムヒョン元大統領が生前よく言及していた“常識”という言葉。この言葉の意味を今、ソン・ウソクが振り返る。
貧しい家庭で育った高卒の弁護士ソン・ウソク(ソン・ガンホ)は、大田(テジョン)で裁判官として働いていたが、退職して釜山(プサン)に帰り、登記・税法専門の弁護士になる。人々は「弁護士がそんなことをするのか」と嘲笑ったが、ソン・ウソクにとって弁護士という職業は金儲けの手段に過ぎず、社会的地位は重要ではなかった。そして彼はダンスクラブの前でも数十枚の名刺を配る。貧乏から抜け出そうとする彼の姿は、普通の家庭の家長となんら変わらない。
優れたビジネス手腕で顧客を集めることに成功した彼は、希望通りマンションに引っ越すなどして成功を収める。その中で国家保安法と関連した釜林(プリム)事件の弁護を担当することになる。この事件には、貧しかった受験生の自分に熱いクッパ(韓国風雑炊)をご馳走してくれたクッパ屋のおばさん(キム・ヨンエ)の息子パク・ジヌ(ZE:A シワン)が関与していた。周囲から引き止められつつ事件を担当したソン・ウソクは、この事件を機に人権弁護士として生きることになる。
「弁護人」は体感温度の高い映画だ。特に法廷ドラマが本格的に繰り広げられる後半部分は、ソン・ガンホの熱演でさらに盛り上がりを見せる。映画が発する熱気は、題材である釜林事件が浮上して始まる。釜林事件とは、1981年第5共和国当時、公安当局が釜山で読書会をしていた学生や教師、会社員など22名を令状なしで逮捕した後、不法に監禁し残酷に拷問した容共操作事件のことだ。公安当局が彼らを共産主義者だと規定した理由は、当時不穏の書とされていた「歴史とは何か」「小人が打ち上げた小さなボール」など、利敵表現物を学習・討論したということだった。
映画は“釜林事件”を機にヒューマンドラマから法廷ドラマへと本格的に転換する。優しい笑顔とユーモアを兼ね備えたソン・ウソクは、乱れた社会に対し断固として言うべきことを言おうとする弁護士ソン・ウソクへと変わる。映画に充満する温もりと人間味もこの地点を過ぎてからは非常識への怒りと真実を明かそうとする情熱に変わる。そして興奮が頂点に達した時、ソン・ウソクの口から私たちが叫びたかった言葉が出てくる。
「韓国の全ての権力は国民から出る。国家とは国民です」
映画はソン・ウソク、あるいはソン・ガンホの映画だと言っても過言ではないほどソン・ウソクを中心に彼の変化を描いている。映画「南營洞1985」よりは「フォレスト・ガンプ/一期一会」のイメージに近い。公安当局の冷たく不気味な空気よりは人の匂い、湯気の立つ温かいクッパが印象深い映画だ。温かさの中でも不快だったり、怒りを覚えることがあっても、最後は切なくなるところがこの「弁護人」に盛り込まれた感情のジェットコースターだ。

まず一つ目は、話の展開速度だ。映画の序盤はソン・ウソクという人物が税法専門の弁護士にならざるを得なかった過程をスピード展開で見せてくれる。しかし、中盤からはそのスピードが徐々に遅くなる。それは恐らくソン・ウソクの感情を観客側に同じスピードで共感してもらおうとする監督の意図だと思われる。観客がソン・ウソクの感情を共有できるように十分な時間を使って描かれたが、これにより映画が少し退屈なものになってしまった。
二つ目は、ソン・ウソクを除いた全ての周辺人物のキャラクターが立体的ではないことだ。これは、ソン・ウソクだけを際立たせるための監督の手法と言えるが、これにより複数の人物が存在感を失った。特にチョ・ミンギ演じるカン検事はソン・ウソクのカリスマ性に適確に応じることができず、イ・ソンミン演じる記者イ・ユンテクも職業の設定上見せる性格以外に人間的な魅力が見られなかった。
その中で最も目立っていたと言える登場人物は、ソン・ウソクとは別の方法で“愛国”を示すチャ・ドンヨン刑事(クァク・ドウォン)だ。チャ・ドンヨン刑事が共産主義者の打倒に没頭する名分は、彼のひと筋の歴史が説明するものが全てである。クァク・ドウォンの好演により、チャ・ドンヨン刑事の存在感はしっかりしたものになった。一番の見所はチャ・ドンヨンがソン・ウソクと舌戦を繰り広げるシーンだ。涙が溢れんばかりの顔でジヌを弁護し、国家について説くソン・ウソクを前にしてもチャ・ドンヨンは動じず、堂々とした態度で自身の行動の正当性を疑わなかった。
三つ目は、事件の調査過程でジヌの拷問シーンが繰り返されたことだ。拷問シーンは「南營洞1985」で飽きるほど見ているためデジャブを感じ、非常に直接的な描写は不快なほどであった。これは、ソン・ウソクが事件に対して更なる怒りを感じるようにさせ、観客たちを動揺させるためのものだが、その結果、温かい雰囲気の映画を重苦しく不快なものにしてしまったのではと思わせた。
「弁護人」は、ソン・ガンホの演技抜きには語れない映画だ。この映画を通して初めてセリフを練習したと言うソン・ガンホは、完璧に近い演技を見せた。彼の演技は幅広いジャンルをカバーできる上、強弱をつけることに長けているという長所を持っている。今回の映画では、彼の演技力がそのまま発揮された。貧困、学歴などのコンプレックスから大学生のデモを客気に駆られた行動だと思っていたソン・ウソクがこの事件をきっかけに社会に関心を持つようになる過程は、ソン・ガンホの眼差しの変化からも分かる。
クッパ屋のおばさんと手を取り合うソン・ウソクと、社会の悪からの握手を振り切るソン・ウソクは、ソン・ガンホの演技によって差別化され、同一視されたりする。力を抜くべきところでは抜き、力を入れるべきところでは力を入れる緩急の調整は、この映画の価値を高める核心的要素だ。3分にも及ぶロングテイクのシーンで彼の真価は発揮され、それと同時にキム・ヨンエ、クァク・ドウォン、オ・ダルス、シワンなどによる適切な演技は映画の完成度を更に高めた。
2012年に公開された映画「26年」は、光州(クァンジュ)民主化運動を弾圧した“あの人”に復讐する内容を描いた作品だ。その1年後、「弁護人」は「26年」の中のあの人の時代に世の中を直視し、常識が通用する世の中を作ろうとした故ノ・ムヒョン元大統領、いや、弁護士ノ・ムヒョン、人間ノ・ムヒョンを描いている。実に皮肉なことである。
「弁護人」は、あえて故ノ・ムヒョン元大統領を思い出さなくても商業映画として適確な完成度と面白さを兼ね備えた映画だ。この映画の善意は、どの時代にも不正に対抗しようとする正義が存在したという事実を教えてくれたことにある。騒然とした社会の中、観客が「弁護人」を見る理由が正にここにあるのではないだろうか。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- キム・ジョンギル
topics