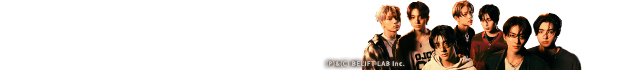Vol.1 ― ハ・ジョンウ「『いつか家族に』はおとぎ話のような話…ハリウッドのアニメーションを参考にした」
※この記事には映画のストーリーに関する内容が含まれています。
 写真=チ・ヒョンジュン
写真=チ・ヒョンジュン
ハ・ジョンウ:僕を可哀想に思ったようだ。思ったよりも良く見て頂いた方々がいる。ここ数日は少し気分が良かった。(9日に)マスコミ向け試写会が終わって昼間からお酒を飲んだ。大きい山は越えたという気持ちでスタッフたちと中華料理店で午後2時から午後10時まで酒を飲んだ。
―食べ物をおいしそうに食べることで有名だ。原作には売血した後、豚レバー炒めと黄酒(中国酒)を飲むシーンが繰り返し登場するので、「いつか家族に」の映画化を聞いたたくさんのファンがハ・ジョンウのモッパン(食べるシーン)を期待した。でも、思ったよりも自制していた。
ハ・ジョンウ:僕が食べるより、劇中の他の登場人物を通じて表現した方が良いと思った。序盤にさつまいもとスンデ(豚の腸詰)を食べるシーンがあるが、そのシーンを強調することは無理だった。
―原作には家族愛を象徴する食べ物として紅焼肉(豚の角煮)が登場するが、映画では餃子に変わった。
ハ・ジョンウ:餃子は普遍的で、老若男女を問わず誰もが好きな一般的で簡単な食べ物じゃないか。編集監督が、作業をしながら餃子とスンデをたくさん食べたと聞いた。観客の方々がこの映画を見た後、餃子を食べたくなったら成功だと思う。カチンコにイメージを一つ入れていたが、それが餃子だった。
―背景が1960年代の忠清南道(チュンチョンナムド)公州(コンジュ)なのに、許三観は方言を全く使わない。
ハ・ジョンウ:原作を見たとき、許三観というキャラクターが韓国なら忠清道出身になるだろうと思った。ノロノロとのんきな性格だけど、言うべきことは全部言う。僕が持っている忠清道出身の人に対するイメージだった。台詞が文語体だったので、それに方言まで入れるのは無理だと思った。あの時代、許三観が生きる村には移民が多いだろうと思った。チョン・マンシクとチョ・ジヌン、イ・ギョンヨンぐらいがニュアンスだけを生かして、他の人は気楽に台詞を言ってほしいと頼んだ。
 ―台詞の一部は原作小説と全く同じだ。映画なのに文語体の台詞をそのまま生かした理由は?
―台詞の一部は原作小説と全く同じだ。映画なのに文語体の台詞をそのまま生かした理由は?
ハ・ジョンウ:文語体の台詞に魅了された。それがユイ・ホアの面白いところの一つだと思った。それを最大限生かしてみようと思った。
―BGMも時代背景とは違って洗練された感じがある。
ハ・ジョンウ:少しおとぎ話のような話じゃないか。美術や音楽もそんなふうに合わせた。それが方言をリアルに生かさなかった理由でもあった。音楽のコンセプトは「モンスターズ・インク」や「トイ・ストーリー」シリーズなどのアニメーション音楽を参考にした。後半部は「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」や「ゴッドファーザー」などから探した。ハリウッドで活動する作曲家と話して“アニメーションのような感じ”を入れようとした。フランス、チェコ、イタリアなどでレコーディングが行われた。
―ハリウッドのアニメーションを参考にした理由は何か?
ハ・ジョンウ:映画が与えるファンタジーを強調したいと思った。売血そのものが胸の痛い行為だ。「いつか家族に」は温かい家族映画になってほしかった。美術や音楽でそのような部分を際立たせたいと思って美術は原色を選び、音楽は説明的でストレートなアニメーション音楽を選んだ。
―子役俳優たちの演技が抜群だ。イルラク役のナム・ダルム、イラク役のノ・ガンミン、サムラク役のチョン・ヒョンソクはみんな素晴らしい演技を見せてくれる。
ハ・ジョンウ:子役選抜の過程が一番重要で、心血を注いだ。撮影の5ヶ月前から1600人の子供を対象にオーディションを実施した。1週間の間に200人見た。オーディション番組のように少しずつ範囲を絞っていった。1人当り10人の候補者と共に毎週金曜日に台本の読み合わせをした。月曜日から木曜日までは子役出身の先生に成長の可能性を見てもらった。最終的に3~5人まで絞った後、テスト撮影をした。その過程で演技の方向性は伝えておいた。子役俳優が混乱する部分が、母親と演技の先生と監督のディレクションがそれぞれ違うということだ。それで演技の先生に窓口を一本化した。演技の先生がしつけまで担当した。現場で子供たちが楽しく撮影できるように大声を出したり、悪口を言わないように気をつけたし、子供たちが遊べるスペースも作った。
―選抜過程で主な基準は何だったのか?
ハ・ジョンウ:柔軟性だ。指示をしたとき、それをこなせるかだった。また、僕とハ・ジウォンの幼い頃の写真を置いてイメージが似たような子を見つけようとした。イルラクとイラクが前作の「群盗:民乱の時代」に出たことは後から知った。
 ―原作を充実に再現した前半部と新しい話になる後半部。2つのパートのトーンを調整するのが難しかったと思う。
―原作を充実に再現した前半部と新しい話になる後半部。2つのパートのトーンを調整するのが難しかったと思う。
ハ・ジョンウ:巫女の祭祀シーンまでが原作にある話だ。後半部は新しく創造した。たくさん悩んだ。様々なバージョンがあった。あるバージョンでは巫女の祭祀シーンがエンディングだった。イルラクがかかった病気についても色々と悩んだ。肺病バージョンもあった。でも、脳炎がその時代に一番合うと思った。お金さえあれば治療できる病気でもあったし。
―中国の小説を映画化した理由は?
ハ・ジョンウ:原作の小説を見たとき、俳優として許三観というキャラクターに興味が湧いた。演出の提案まで受け入れたのも面白さと関心のためだった。許三観は表と裏が違う。無愛想だけど、心の中では泣いている。そのような二面性が魅力的で現実的だと思った。演技において、たくさんのことが表現できる立体的なキャラクターだった。他のキャラクターも個性的で面白かった。
―許三観は長男のイルラクが自分の子でないことを知り、妻ホ・オクラン(ハ・ジウォン)に過去を尋ねる。本人は女性の過去に寛大な方なのか?
ハ・ジョンウ:ははは、誰だってそんな経験はあるじゃないか。相手の過去をとことん追及し、知りたがる。聞いてはいけないことまで聞いて、何だか気持ちが悪くなった経験。若い頃に誰もが経験する過程だと思いながら演技した。
―マスコミ試写会後の記者懇談会で、「いつか家族に」を初心を思い出させるターニングポイントのような作品だと表現した。
ハ・ジョンウ:俳優として怠けるようになった部分もあったし、興味を失った部分もあった。マンネリ化したとふと思うときがあった。気を引き締めて生きていかなければならないと思った。その頃「ローラーコースター」の撮影を決心した。ほとんど毎日映画を撮っているが、監督として参加してみたら、また違っていた。人が見え始めた。僕が通り過ぎてしまった小道具チームの末っ子など、スタッフの一人一人が見えてきた。「いつか家族に」は本格的な商業映画と評価される作品ではないだろうか。大学時代に映画をしていたときの気持ち、撮影現場に行くときの緊張感などが感じられた。「こうしたものが初心だな」と思った。「いつか家族に」は映画、そして一緒にする同僚への尊敬心をもう一度感じさせた作品だった。
―次回作の計画は?
ハ・ジョンウ:「暗殺」が最終段階に入った。「いつか家族に」が終わってから一日休んで上海に行き、「暗殺」を撮影した。「いつか家族に」を終えた後なので、チェ・ドンフン監督とはあえて言わなくても通じる部分がある。「暗殺」以降に撮影を開始する「お嬢さん」という作品も、そのような意味でパク・チャヌク監督としてみたいと思った。俳優として映画を撮ることも重要だが、映画を作る人間として先輩監督たちはどうやって映画を作っているのか気になった。当分は俳優として活動を続けていくと思う。ハリウッドからの話もあったが、別に進展はない。提案はあったが、それほど興味が湧かなかった。「暗殺」と「お嬢さん」の方がもっと感じが良い。
 写真=チ・ヒョンジュン
写真=チ・ヒョンジュン映画「いつか家族に」は、妙な映画だ。1960年代を背景にしているが、洗練された雰囲気がある。また、父性愛を題材にしているが、面白い部分がより多い。これは、主演兼演出を務めたハ・ジョンウの性向が反映されたためだ。前半部では中国の作家ユイ・ホア(余華)の原作小説「許三観売血記」を忠実に再現するが、後半部では新しい設定を入れて緊張感を与える。
ハ・ジョンウの演出デビュー作「ローラーコースター」(2013年)は彼の好み通りに作った“利己的な作品”だったが、「いつか家族に」は人々とのコミュニケーションに重点を置いた作品だ。原作との比較から自身の初心を思い出させるターニングポイントになった理由まで、ハ・ジョンウは「いつか家族に」にまつわる様々なエピソードを聞かせてくれた。
ハ・ジョンウ:僕を可哀想に思ったようだ。思ったよりも良く見て頂いた方々がいる。ここ数日は少し気分が良かった。(9日に)マスコミ向け試写会が終わって昼間からお酒を飲んだ。大きい山は越えたという気持ちでスタッフたちと中華料理店で午後2時から午後10時まで酒を飲んだ。
―食べ物をおいしそうに食べることで有名だ。原作には売血した後、豚レバー炒めと黄酒(中国酒)を飲むシーンが繰り返し登場するので、「いつか家族に」の映画化を聞いたたくさんのファンがハ・ジョンウのモッパン(食べるシーン)を期待した。でも、思ったよりも自制していた。
ハ・ジョンウ:僕が食べるより、劇中の他の登場人物を通じて表現した方が良いと思った。序盤にさつまいもとスンデ(豚の腸詰)を食べるシーンがあるが、そのシーンを強調することは無理だった。
―原作には家族愛を象徴する食べ物として紅焼肉(豚の角煮)が登場するが、映画では餃子に変わった。
ハ・ジョンウ:餃子は普遍的で、老若男女を問わず誰もが好きな一般的で簡単な食べ物じゃないか。編集監督が、作業をしながら餃子とスンデをたくさん食べたと聞いた。観客の方々がこの映画を見た後、餃子を食べたくなったら成功だと思う。カチンコにイメージを一つ入れていたが、それが餃子だった。
―背景が1960年代の忠清南道(チュンチョンナムド)公州(コンジュ)なのに、許三観は方言を全く使わない。
ハ・ジョンウ:原作を見たとき、許三観というキャラクターが韓国なら忠清道出身になるだろうと思った。ノロノロとのんきな性格だけど、言うべきことは全部言う。僕が持っている忠清道出身の人に対するイメージだった。台詞が文語体だったので、それに方言まで入れるのは無理だと思った。あの時代、許三観が生きる村には移民が多いだろうと思った。チョン・マンシクとチョ・ジヌン、イ・ギョンヨンぐらいがニュアンスだけを生かして、他の人は気楽に台詞を言ってほしいと頼んだ。

ハ・ジョンウ:文語体の台詞に魅了された。それがユイ・ホアの面白いところの一つだと思った。それを最大限生かしてみようと思った。
―BGMも時代背景とは違って洗練された感じがある。
ハ・ジョンウ:少しおとぎ話のような話じゃないか。美術や音楽もそんなふうに合わせた。それが方言をリアルに生かさなかった理由でもあった。音楽のコンセプトは「モンスターズ・インク」や「トイ・ストーリー」シリーズなどのアニメーション音楽を参考にした。後半部は「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ」や「ゴッドファーザー」などから探した。ハリウッドで活動する作曲家と話して“アニメーションのような感じ”を入れようとした。フランス、チェコ、イタリアなどでレコーディングが行われた。
―ハリウッドのアニメーションを参考にした理由は何か?
ハ・ジョンウ:映画が与えるファンタジーを強調したいと思った。売血そのものが胸の痛い行為だ。「いつか家族に」は温かい家族映画になってほしかった。美術や音楽でそのような部分を際立たせたいと思って美術は原色を選び、音楽は説明的でストレートなアニメーション音楽を選んだ。
―子役俳優たちの演技が抜群だ。イルラク役のナム・ダルム、イラク役のノ・ガンミン、サムラク役のチョン・ヒョンソクはみんな素晴らしい演技を見せてくれる。
ハ・ジョンウ:子役選抜の過程が一番重要で、心血を注いだ。撮影の5ヶ月前から1600人の子供を対象にオーディションを実施した。1週間の間に200人見た。オーディション番組のように少しずつ範囲を絞っていった。1人当り10人の候補者と共に毎週金曜日に台本の読み合わせをした。月曜日から木曜日までは子役出身の先生に成長の可能性を見てもらった。最終的に3~5人まで絞った後、テスト撮影をした。その過程で演技の方向性は伝えておいた。子役俳優が混乱する部分が、母親と演技の先生と監督のディレクションがそれぞれ違うということだ。それで演技の先生に窓口を一本化した。演技の先生がしつけまで担当した。現場で子供たちが楽しく撮影できるように大声を出したり、悪口を言わないように気をつけたし、子供たちが遊べるスペースも作った。
―選抜過程で主な基準は何だったのか?
ハ・ジョンウ:柔軟性だ。指示をしたとき、それをこなせるかだった。また、僕とハ・ジウォンの幼い頃の写真を置いてイメージが似たような子を見つけようとした。イルラクとイラクが前作の「群盗:民乱の時代」に出たことは後から知った。

ハ・ジョンウ:巫女の祭祀シーンまでが原作にある話だ。後半部は新しく創造した。たくさん悩んだ。様々なバージョンがあった。あるバージョンでは巫女の祭祀シーンがエンディングだった。イルラクがかかった病気についても色々と悩んだ。肺病バージョンもあった。でも、脳炎がその時代に一番合うと思った。お金さえあれば治療できる病気でもあったし。
―中国の小説を映画化した理由は?
ハ・ジョンウ:原作の小説を見たとき、俳優として許三観というキャラクターに興味が湧いた。演出の提案まで受け入れたのも面白さと関心のためだった。許三観は表と裏が違う。無愛想だけど、心の中では泣いている。そのような二面性が魅力的で現実的だと思った。演技において、たくさんのことが表現できる立体的なキャラクターだった。他のキャラクターも個性的で面白かった。
―許三観は長男のイルラクが自分の子でないことを知り、妻ホ・オクラン(ハ・ジウォン)に過去を尋ねる。本人は女性の過去に寛大な方なのか?
ハ・ジョンウ:ははは、誰だってそんな経験はあるじゃないか。相手の過去をとことん追及し、知りたがる。聞いてはいけないことまで聞いて、何だか気持ちが悪くなった経験。若い頃に誰もが経験する過程だと思いながら演技した。
―マスコミ試写会後の記者懇談会で、「いつか家族に」を初心を思い出させるターニングポイントのような作品だと表現した。
ハ・ジョンウ:俳優として怠けるようになった部分もあったし、興味を失った部分もあった。マンネリ化したとふと思うときがあった。気を引き締めて生きていかなければならないと思った。その頃「ローラーコースター」の撮影を決心した。ほとんど毎日映画を撮っているが、監督として参加してみたら、また違っていた。人が見え始めた。僕が通り過ぎてしまった小道具チームの末っ子など、スタッフの一人一人が見えてきた。「いつか家族に」は本格的な商業映画と評価される作品ではないだろうか。大学時代に映画をしていたときの気持ち、撮影現場に行くときの緊張感などが感じられた。「こうしたものが初心だな」と思った。「いつか家族に」は映画、そして一緒にする同僚への尊敬心をもう一度感じさせた作品だった。
―次回作の計画は?
ハ・ジョンウ:「暗殺」が最終段階に入った。「いつか家族に」が終わってから一日休んで上海に行き、「暗殺」を撮影した。「いつか家族に」を終えた後なので、チェ・ドンフン監督とはあえて言わなくても通じる部分がある。「暗殺」以降に撮影を開始する「お嬢さん」という作品も、そのような意味でパク・チャヌク監督としてみたいと思った。俳優として映画を撮ることも重要だが、映画を作る人間として先輩監督たちはどうやって映画を作っているのか気になった。当分は俳優として活動を続けていくと思う。ハリウッドからの話もあったが、別に進展はない。提案はあったが、それほど興味が湧かなかった。「暗殺」と「お嬢さん」の方がもっと感じが良い。
- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- キム・ユンジ
topics