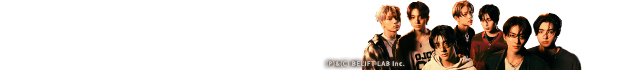「ファジャン」イム・グォンテク監督、102作目にして自分らしくない作品に挑戦した理由とは

1962年の「豆満江よさらば」を皮切りに、興行性と作品性の二兎を手に入れた「シバジ」(1987年)、「ハラギャティ」(1989年)、「将軍の息子」(1990年)、「風の丘を越えて/西便制」(1993年)、「春香伝」(2000年)、カンヌ国際映画祭で監督賞という栄誉をもたらした「酔画仙」(2002年)まで。イム・グォンテク監督はいつも韓国人の“恨”(ハン:韓国特有の恨みの感情)と芸術人の人生に疑問を持ち、これを極めて美しい映像美でスクリーンに盛り込んだ。
そんな彼が102本目の新作「ファジャン」(制作:ミョンフィルム)を通して自らの限界を越える挑戦を繰り広げた。一歩ずつ死に近づく妻と、人生でもっとも輝く女性の間で葛藤する中年男性の物語は、イム・グォンテク監督の従来の作品とは流れが違う。イム・グォンテク監督は自ら抜け出すにはぴったりの物語であるため、「ファジャン」に飛び込んだと力を込めて話した。
「ファジャン」はキム・フン作家の2004年「第28回イ・サン文学賞」で大賞を受賞した小説を原作に、癌になった妻が死に近づくほど他の女性を深く愛することになった男性の悲しき葛藤を描いた映画だ。生と死、愛と煩悶という人間の普遍的な素材をイム・グォンテク監督だけの成熟した視点で描いた。
キム・フン作家特有の簡潔な文体をスクリーンに移す作業は、100本以上の映画を撮ってきた監督にとっても決して簡単な作業ではなかった。イム・グォンテク監督は、原作が持つ空気感を100%そのままカメラに移すことができなければ、目を閉じるようになるほどリアルな現実性に重きを置くことにし、これが成功した。女優キム・ホジョンが全裸での露出を披露した浴室シーンがその例だ。死のために崩れていく女性が夫の前で感じたであろう絶望と羞恥心を、イム・グォンテク監督は妥協せずカメラに映した。
80歳を目前にしている監督の挑戦に、世界の映画人も答えた。「ファジャン」は第71回ベネチア国際映画祭を始め、トロント、バンクーバー、釜山(プサン)、ハワイ、ストックホルムなど世界16ヶ国の映画祭に招待され、好評を得た。
イム・グォンテク監督と作業した俳優たちは現場での彼の姿について「撮影に入れば、目に聡明さが浮かぶ方」と褒め称えた。確かにインタビューの途中で妻に電話をかけ、知らないことを聞き、息子(クォン・ヒョンサン)に対する賛辞に笑いをこらえるなど、天真爛漫なところがある彼だったが、映画に関する話をする時だけは目に力が入った。彼の情熱いっぱいの眼差しを長く現場で見られることを願う。

イム・グォンテク:長く映画の仕事をやってきたため、年を取っただけに、生きてきた歳月ほど、積み重ねた経験値ほど映画に反映される。今になって若い映画を作ろうとしても出来るわけではなく、今の年齢よりもっと大人っぽい映画を作ろうとしても僕の思い通りにはならなかった。今まで僕の人生で蓄積したものをベースに、世の中を見るようになるということを知った。「ファジャン」がそうだ。80歳近い僕が作った世の中を見る視線を20代、40代、60代の観客がどのように受け入れるのかが心配で気になる。
―原作は短編小説だ。映画化を決心したきっかけは何か。
イム・グォンテク:従来の僕の作品は韓国文化、僕世代の受難史を主に書いてきた。あまりにも長い間そのような物語を描いてきたため、自分自身から抜け出したいと思った。監督としての寿命、ダイナミックさについて悩んでいたところ、ミョンフィルムが「ファジャン」映画化の提案をしてきた。「ファジャン」の物語なら、従来の僕から抜け出せるという思いから演出をすることになった。
―キム・フンの原作は特有の短く、力のある文体が重要な作品だ。これを映像に移す作業は簡単ではなかったと思う。
イム・グォンテク:そうだ。キム・フン作家の文章が持つ力、迫力を映画に盛り込もうとしたが、いざやってみると上手くいかなかった。完全にジャンルが異なる上に小説自体がものすごく優れているじゃないか。下手したら大きな恥をかくと思った。あ、恥も恥だが、どうしても消化不良になりそうだった。キム・フン作家の文章をそのまま映像に盛り込むことが出来なければ、映画「ファジャン」だけの長所を何にするか悩み、“リアルさ”“現実性”溢れる映画を作ることにした。だからと言って小説に現実味がないというわけではない。小説よりも、さらに人生そのものにリアルさを吹き込もうとしたということだ。
―「ファジャン」はイム・グォンテク監督の経歴の中でも目を引く作品だが、主演俳優アン・ソンギにとっても意味のある挑戦だった。
イム・グォンテク:アン・ソンギが演じるオ・サンムは、妻が死に近づいていく苛立ちを何年も耐え抜き、献身する人物だ。死んでいく妻の隣で夜を更かしながらも、好きな女を心に抱くキャラクターだが、間違って演じると嫌悪感を抱くようになる危険な役割だ。そのような危険を乗り越えられる俳優として誰がいるかと考えたときに、アン・ソンギほどの俳優はいない。演技を上手にやっても見苦しくなりかねないキャラクターを、アン・ソンギが上手く演じてくれた。

イム・グォンテク:俳優にとっては映画内での人生だけでなく、映画の外での人生もあるじゃないか。「ファジャン」のオ・サンムは、映画の外での動きが重要なキャラクターだった。さらにアン・ソンギも僕も、お互いに点検できている部分があるじゃないか。年を取ると、映画の外での生きてきた過程も見るようになった。
―キム・ホジョンをキャスティングする過程も簡単ではなかったと思うが。
イム・グォンテク:一体誰を選んだらいいのか…果たしてどんな女優が妻役をやると名乗ってくれるか…。女性としてどんな魅力も映画で発散できない役じゃないか。僕も長いこと映画を作ってきたが、このようなキャラクターは初めてだった。そんな中、ミョンフィルムがキム・ホジョンを推薦してくれた。妻のキャラクターは病気な人物でもあるが、病気になる前は非常に魅力的な人物だったと思う。その2つをすべて満足させる必要があったが、キム・ホジョンを見ると出来そうだと思った。しかも、このようにリスクの多い役を演じると名乗り出てくれた女優は何かが違うと思ったし、勇気もすごかった。
―キム・ホジョンが全裸を露出した浴室シーンが話題だ。
イム・グォンテク:映画に決定的なリアルさを与えるシーンが、まさにそのシーンだった。最初は半裸で撮影した。撮ってみるとどうも違った。恐らく他の女優だったら、全裸はお願いできなかったと思う。妻役の出演を決めたのは、普通の女優ではないということを意味する。キム・ホジョンの信念、並ならぬ勇気が感じられたため、全裸になることをお願いした。醜い姿を想像するだろうけど、映画には美しく映ると。あなたが露出を決心するまで、このセットを解体しないで待つと。キム・ホジョンは2~3時間で撮影すると決心した。結果として、映画にリアルさを与える非常に重要なシーンが誕生した。もちろん、映画は生き生きとしたが、監督としていつも片隅では申し訳ない気持ちがある。
―キム・ギュリとは「下流人生 ~愛こそすべて~」(2004年)以来、2度目の作業だ。
イム・グォンテク:「下流人生 ~愛こそすべて~」の時まで、キム・ギュリがこんなにセクシーな女優だとは思わなかった。2年前、釜山(プサン)国際映画祭の開幕式を見ていたところ、あるダンサーがダンスをとても圧倒的な雰囲気で踊っていた。「あの人は誰で、どうしてあんなにダンスが上手なのか」と聞いたが、それがキム・ギュリだった。キム・ギュリのそのようなセクシーな面を生かせばいいと思い、今回キャスティングした。

イム・グォンテク:僕はこれまで海外の映画祭をたくさん回ったが、こんな反応はまた初めてだった。外国人たちに「僕の映画のどこがそんなにずば抜けて良かったのか」と尋ねると、「リアルなところ」だと話した。
―1歩間違えると、不倫ドラマに見えがちだ。オ・サンムを生と死の間にいる男として描くために注意した点があるのか。
イム・グォンテク:オ・サンムは、妻の長い闘病生活にとても疲れているはずだ。それでも献身的に妻を看護する人間としての理知的な面に注目して欲しい。そこまで見てくれるかは分からないが(笑) 僕みたいに80歳近い人の考えはそうだ。
―愛妻家で有名だ。
イム・グォンテク:もし、妻がそんなに長い病気になり、苛立たせることをすれば、その時も愛妻家でいられるかは分からない。人間として充実する道理、理知的な面が人間にとって必要だという話をする映画を撮っておいても、良く分からない。
―今後描いてみたい物語があるのか。
イム・グォンテク:きっともっと話したいことがあると思うが、100本の作品をいい加減に作ったため、全部忘れてしまった(一同爆笑) 生きていく中で、どんな物語にどんな風に出会えるかは分からない。

- 元記事配信日時 :
- 記者 :
- キム・スジョン、写真 : イ・ソンファ、映画「ファジャン」スチールカット
topics